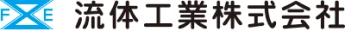技術資料 気体編 2.気体の流量単位(体積流量)
1.気体の流量単位(体積流量)
気体は温度、圧力により体積が変化する圧縮性流体のため体積流量では温度、圧力の状態を考慮して表す必要があります。
下の図は空気 1.293kg の体積を表していて、左が 1 atm、0℃の基準状態の体積で 1m3 になり直径 1.2408m の球の大きさに相当します。
右は圧力 0.5MPa(G)、温度 20℃ の体積で 0.1808m3、直径 0.7016m の球の大きさに相当します。
この左右の空気の球の質量(重さ)は、どちらも 1.293kg と同じです。
この図の大きさは原寸比となっていますので加圧された気体の体積がどのように変わるのかが客観視できると思います。
空気の圧力温度変化による体積
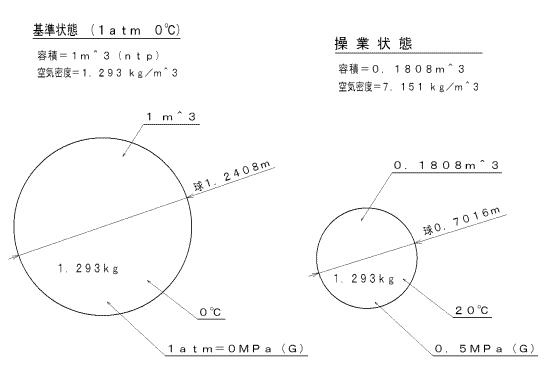
図は気体の「体積」が「圧力」、「温度」の変化で、どう変わるかを説明していますが流量とは、この体積が時間あたり、どれだけ流れているかを表したものですので下記の単位を付けて表すことになります。
SI単位での体積流量はm3/s またはm3/min、m3/h、L/s、L/min、L/h で表します。
このとき0℃、1atm(大気圧)での体積を基準状態(Normal状態)と呼びm3/s(ntp)、m3/min(ntp)、m3/h(ntp) 、L/h(ntp)・・・のように (ntp) の添え字を付けて表示します。
(ntp) = normal temperature pressure
弊社ではJIS B 7551:1999 解説3.3 用語の定義に従い(ntp) を用いています。
基準状態(0℃、1atm)での気体の体積はm3(ntp)、L(ntp) で表し
時間当たりの流量はm3/h(ntp)、L/h(ntp)で表します。
体積がm3(ntp)なので、m3(ntp)/h、m3(nor)/h と表示している流量計makerもあ りますが弊社では m3/h(ntp)、L/h(ntp) のように末尾に (ntp) の添字を記載いたします。
流量計を流れる気体の操業状態(Operation状態)では温度25℃、圧力100kPa(G)などの加圧された状態で流れることが多いのですが、知りたいのは基準状態での流量であることが多く操業状態の体積流量を基準状態の体積流量に換算して m3/h(ntp) と表示しています。
空気1.293kg、温度0℃、圧力1atm の体積
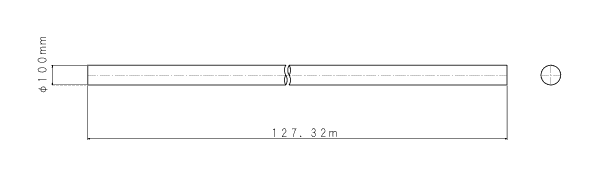
上の空気の例を実際の配管の体積で考えると、内径100mmの配管例では長さが 127.32mになります。
この配管内の圧力は1atm(大気圧)で温度は0℃の基準状態です。この例では圧力1atm=0MPa(G)、温度0℃で流れている空気の流量は操業状態では1時間で見れば 1m3であり、この体積を「基準状態 1atm 0℃」で表しても 1m3になります。
流量計の仕様としては1m3/h(ntp) 1atm 0℃ AIR と表します。
しかし、この1atm 0℃ での操業はあまり多くは無いようです。配管内に気体を流すには多くの場合が加圧して流し、温度も 0℃以外が多いようで、下が実際の操業状態の多い例です。
内径100mmの配管例では長さが 127.32m になり、1m3の体積ってけっこう大きいように感じます。
空気1.293kg、温度20℃、圧力0.5MPa(G) 操業状態の体積
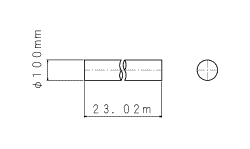
上の右側の図、空気の球の体積を内径100mmの配管に例えると長さが 23.02mに相当します。一般的な配管内を流れる気体はこのような加圧状態で温度も0℃以外が多いのですが、流量計ではこの操業状態の流量を計測しています。しかし、操業状態の圧力、温度は操業場所、環境によってまちまちであるために、計測した体積流量の単位を操業状態で表示すると気体の使用量の把握が理解しにくくなるために流量単位として、上の「基準状態 1atm 0℃」で表すことが多くあります。この基準状態 1atm 0℃ を流量単位として(ntp)を添え字として用います。
この例では圧力 0.5MPa(G) 、温度 20℃ で流れている空気の流量は操業状態を1時間で見れば 0.1808m3 であるが、この体積を「基準状態 1atm 0℃」で表すと 1m3 になります。
流量計の仕様として 1m3/h(ntp) 0.5MPa(G) 20℃ AIR と表します。
この (ntp) で表す流量単位をノルマル流量とか基準状態流量と呼んでいます。
弊社で製造する流量計で最も多い表示方法になります。
操業状態のままの体積流量で表す場合は、圧力 0.5MPa(G)、温度20℃ で流れている空気の流量は操業状態を1時間で見れば 0.1808m3 ですので、流量計の仕様として 0.1808m3/h(op) 0.5MPa(G) 20℃ AIR と表します。
この(op)で表す流量単位をオペレーション流量とか操業状態流量と呼んでいます。
この (op) の添え字は (ntp) と区別するためにたいへん重要となります。つまり圧力 0.5MPa(G) 、温度20℃で流す空気の体積流量を (ntp) で表示するか (op) で表示するかで、5.5倍の体積差があるために基準状態の (ntp) で表すのか、操業状態の (op)で表すのかをはっきり理解して区別してから流量計を発注、製作、使用する必要があります。
なお、質量流量 kg/h kg/min などの質量単位で表す場合は基準状態、操業状態の区別はありません。
SI 単位以前は Nm3/h 、 NL/min など Normal の N を付けていましたがSI 単位の力を表す NEWTON の N と混同するために SI 単位統一後は使用されなくなりました。
※1 日本工業規格 JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計解説 3.3 用語の定義 次の例のように表示すべきであると考える。
Sm3/h → m3/h [stp] Nm3/h → m3/h [ntp]
例外処置として刻印や印刷などで [ ] がくずれる場合は、( )表示で代用している。
※2 社団法人 日本計量機器工業連合会 流量計技術委員会
「計量法改正に伴う SI 単位移行に関する対応」 平成5年11月
工業会の対応についてとし誤解の生じやすい単位については、原則として次の表記を用います。
2.気体の体積
使用状態での体積は、m3、l もしくは L などの表記とします。
基準状態(0℃、1気圧)での体積は m3[nor] あるいは m3[ntp] などを用いて表す。
標準状態(20℃、1気圧)での体積は m3[std] あるいは m3[stp] などを用いて表す
弊社での体積流量に関する用語は下記の定義としています。
| 状 態 | 仕 様 | 漢字表現 | カタカナ表現 | 添え字 |
| 基準状態での流量 | 1 atm 0℃ | 基準状態流量 | ノルマル流量 | (ntp) |
| 操業状態での流量 | 各 圧力、温度 | 操業状態流量 | オペレーション流量 | (op) |
| 標準状態での流量 | 1 atm 20℃ | 標準状態流量 | スタンダード流量 | (stp) |
特殊表示について
操業状態での流量に「タービンメータ」の気体の流量表で「Actual L/min 、Actual mL/min」 と記載しております。
これは製造元の米国FTI社での表示が Operation を「Actual」と表現しているために同様の流量表示としているためです。
Actual L/min = L/min(op) とお考えください。
面積流量計(気体用)の必要仕様
| 仕様 | 弊社での呼び | 記号 | 例 | 単位例 |
| 流体名称 | 流体名 | N2 | - | |
| 流体密度 ( 1atm 0℃ ) | ノルマル密度 | ρ0 | 1.25 | kg/m3(ntp) |
| 流体密度 (操業時気体密度) | オペレ-ション密度 | ρ1 | 2.3145 | kg/m3(op) |
| 操業状態の温度 | 測定流体温度 | 20 | ℃ | |
| 操業状態の圧力 | 測定流体圧力 | 100 | kPa(G) | |
| 測定流量(目盛)範囲 | 流量範囲 | 200~2000 | m3/h(ntp) | |
| 設計温度 | 設計温度 | 50 | ℃ | |
| 設計圧力 | 設計圧力 | 150 | kPa(G) | |
| 耐圧 | 耐圧試験圧力 | 225 | kPa(G) |
注記1.上記例のように体積流量m3/h(ntp)の添え字(ntp)の意味する0℃、1atmと測定流体温度20℃、測定流体圧力100kPa(G)の操業状態とは別ですのでご注意ください。
注記2.Catalogに記載の流量範囲は体積流量m3/h(ntp)またはL/h(ntp)で表示し測定流体温度20℃、測定流体圧力1atmの操業状態としていますのでご注意ください。
注記3.設計温度、設計圧力とは流量計のHard部分設計での仕様であり、密度を決める要素とは別の必要仕様ですのでご注意ください。強度計算などに用いる温度、圧力になります。
注記4.操業時気体密度はノルマル密度が判っている場合は計算によって求めます。
気体の基準状態 0℃、1atm(大気圧)を 基準状態と呼ぶのに対して、20℃、1atm(大気圧)を スタンダードと称してm3/h(stp) or m3/h(std) と表す場合がありますが、この表現は各業種、各業界によって異なるようで特に温度を 20℃、25℃、17℃、15.6℃・・・と、圧力も1atm、1bar ・・・などはっきりと定義されているものではないようです。
その業界、業種の Standard があるようですが統一されているものではないようです。
よって、(stp) の添え字のみでなく仕様書などで[温度20℃、1atm]など明記したほうが誤解が生じないと考えられています。
弊社では JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計 解説3.3 用語の定義 に従って (stp) を用い温度は一般的な 20 ℃ 、圧力は 1 atm = 101.33 kPa(abs) を用いています。
Normal 状態の流量表示 m3/h(ntp) と Operation 状態の流量 m3/h(op) の関係は次式で表せます。
Q(ntp) = Q(op) × (δop / δntp )
Q(op )= Q(ntp)×( δntp / δop )
Q(stp )= Q(ntp)×( 293.2 / 273.2 ) = Q(ntp)× 1.0732
Q(ntp )= Q(stp)×( 273.2 / 293.2 ) = Q(stp)× 0.9318
ここで δop は気体の操業状態の密度で例えば 25℃、100 kPa(G) の空気の密度は下記の計算によって求めます。
求める密度= 1.293×273.2/(273.2+25)×(101.33+100)/101.33
= 1.293×(273.2/298.2)×(201.33/101.33)
= 1.293×0.9161636×1.98687
= 1.293×1.820298
= 2.3536 kg/m3(op)
操業状態の気体の密度の計算式
δop = δntp×273.2/(273.2+T1)×(101.33+P1)/101.33
δntp : kg/m3(ntp) 気体の密度(基準状態)
δop : kg/m3(op) 気体の密度(操業状態)
T 1 : ℃ 気体の温度(操業状態)
P 1 : kPa(G) 気体の圧力(操業状態)
| SI 単位で使用される体積流量 | ||
| m3/s | m3/min | m3/h |
| L/s | L/min | L/h |
| 気体の場合の添え字 ( )カッコ 部分が添え字 | ||
| m3/s(ntp) | m3/min(ntp) | m3/h(ntp) |
| L/s(ntp) | L/min(ntp) | L/h(ntp) |
| m3/s(op) | m3/min(op) | m3/h(op) |
| L/s(op) | L/min(op) | L/h(op) |
| SI 単位で使用される質量流量 | ||
| kg/s kg/sec | kg/min | kg/h |
| t/s t/sec | t/min | t/h |
※備考
JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計 3.定義にて基準状態 温度0℃、圧力101.3kPaの状態 と記載されていますが化学分野の文献など見ると0℃、1atmを標準状態と表現しています。
JIS B 7551:1999 フロート形面積流量計 解説3.3 用語の定義でも0℃、1atm の状態を JIS M 8010 天然ガス計量方法 では 標準状態
としていると記載しています。
このように JIS 規格、業界等で表現の違いが存在していることも注意が必要です。
体積流量に対して容積流量の用語がありますが、体積=容積 と考え同じ意味です。
質量流量の SI単位はkg/sまたはkg/min、kg/hですが、この場合は温度、圧力に関わらず質量そのもの ですので、流量表示にこのようなNormal状態、Operation状態を考慮する必要がありません。
また、蒸気も気体として考えますが蒸気には基準状態はありえませんので流量単位はm3/hなどの容積流量、kg/hなどの質量流量の操業状態流量で表示して基準状態流量(ntp)は使用しません。
流量とは関係ないですが、温度、圧力を表現するのに[AMB.]と表示する場合があるようですが、 この表現もはっきりとした規まりがないようで和訳すると[環境]Ambience になるのでしょうか?
どこの環境なのでしょうか?流量計を設計製作するには20℃、100kPa(G)などの明確な数値が必要な ので仕様書を作成される場合は数値によることをお願いいたします。
2.ボイル・シャルルの法則
一定の質量の気体の体積[V]は、絶対圧力[P]に反比例し、絶対温度[T]に比例する。
これを「ボイル・シャルルの法則」と云います。
絶対温度[T1]、絶対圧力[P1]、体積[V1]の気体が
絶対温度[T2]、絶対圧力[P2]、体積[V2]になった場合は次の関係式が成り立つ。
式を変形すると
計算例1. (冒頭 1.気体の流量単位の例を当てはめると)
0℃、1atm の空気 1m3 は
[T1]=273.2+0 K [P1]=101.33+0 kPa(abs) V1=1m3
20℃、0.5MPa(G) の空気の体積はいくらか
[T2]=273.2+20 K [P2]=101.33+500 kPa(abs) V2=?
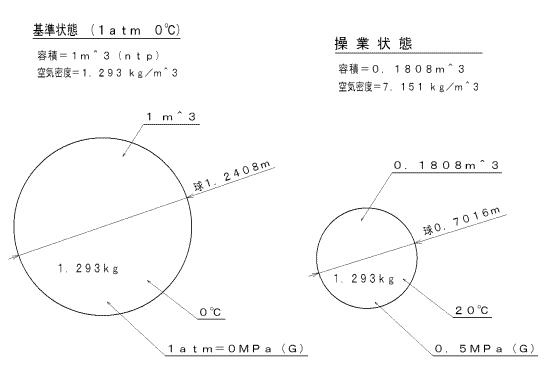
式に当てはめて計算すると
よって、V2の体積は0.1808m3となります。
計算例2.
300kPa(G)において、20℃の体積100リットルの気体を100kPa(G)、温度100℃にしたら体積は何リットルになるか。
答え
P1 : 300kPa(G)=101.33+300 kPa(abs)
T1 : 20℃ =273.2+20 K
V1 : 100リットル
P2 : 100kPa(G)=101.33+100 kPa(abs)
T2 : 100℃ =273.2+100 K
以上を式に代入すると
計算例3.
圧力200kPa(G)、温度20℃の空気が100m3/h(ntp)で流れている。
操業状態での流量(Operation流量)はいくらか?
答え
V2 : 20℃、200kPa(G)でのOperation流量 体積=流量と考える
P2 : 200+101.33 kPa(abs)
T2 : 273.2+20 K
V1 : 100m3/h(ntp) 体積=流量と考える
P1 : 1atm=101.33 kPa(abs)
T1 : 0℃ =273.2 K
以上を式に代入すると
計算例4.
圧力200kPa(G)、温度20℃の空気が36.08m3/h(OP)で流れている。
Normal流量(基準状態:1atm、0℃)はいくらか?
答え
V2 : Normal流量 体積=流量と考える
P2 : 1atm=101.33 kPa(abs)
T2 : 0℃ =273.2 K
V1 : 36.08m3/h(OP) 体積=流量と考える
P1 : 200+101.33 kPa(abs)
T1 : 20℃=20+273.2 K
以上を式に代入すると
計算例5.
空気の流量100m3/h(ntp)を圧力1atm、温度20℃の流量に換算するといくらになるか?
答え
V2 : 1atm、20℃での流量 体積=流量と考える
P2 : 1atm=101.33 kPa(abs)
T2 : 20℃ =20+273.2 K
V1 : 100m3/h(ntp) 体積=流量と考える
P1 : 1atm =101.33 kPa(abs)
T1 : 0℃ =273.2 K
以上を式に代入すると
備考1. Normal流量V1(1atm、0℃)を1atm、20℃の状態の流量に換算するには係数1.0732を乗じる。(7.32%増)
備考2. 1atm、20℃の状態の流量V2をNormal流量(1atm、0℃)に換算するにはV2に係数1/1.0732(0.9318)を乗じる。
計算例6.
外気温度30℃、配管を流れる流体温度が低温で流量計の指示器温度が0℃になったと仮定して指示器が密閉構造の場合に指示器の内部圧力はいくらになるか?
外気の気圧を大気圧=101.3kPa(abs) として考える。
(流量計を配管に取り付ける前の指示器内部は外気温度30℃で大気圧とした場合)
答え
V1=V2 指示器内の容積
P1 : 1atm=101.33 kPa(abs)
T1 : 30℃ =30+273.2 K
P2 : 指示器内の圧力
T2 : 0℃ =273.2 K
式に代入すると
P2 = (P1×V1×T2)/(T1×V2)
=(101.33×273.2)/(30+273.2)
=27683.35/303.2
=91.30
よって、指示器内部の圧力は91.30 kPa(abs) と負圧になる。
101.33-91.30 = 10.03 kPa
外気との間に約10kPaの差圧が発生することになります。
気体用流量計を扱うには、この「ボイル・シャルルの法則」を流量計機種を選定するために行う計算「換算」と、仕様と異なる条件で使用している場合に実量(真値)を計算で求める「補正」に多用しています。
ボイルの法則(体積と圧力の関係)
1662年、イギリスの科学者ボイルが真空ポンプと水銀気圧計を用いて「温度が一定ならば、一定質量の気体の体積[V]は圧力[P]に反比例する」という、ボイルの法則を発見した。
シャルルの法則(体積と温度の関係)
1787年、フランスの科学者シャルルが気体の熱膨張を研究して「圧力が一定ならば、一定質量の気体の体積[V]は温度が1℃上昇
するごとに、0℃の時の体積の1/273.2ずつ増加する」というシャルルの法則を発見した。
4.摂氏温度セルシウス(℃)と絶対温度ケルビン(K)
上の式のT1 は絶対温度で表します。
日常用いる温度はセルシウス温度、摂氏℃を多用しますので絶対温度には換算が必要です。
絶対温度は単位(K)ケルビンで表され、絶対温度0(K)は-273.2℃です。
つまり
絶対温度 = 摂氏 + 273.2 (K) となります。
セルシウス : スウェーデンのアンデルス・セルシウスが1742年に考案した温度体系。
ケルビン : イギリスのウイリアム・トムソンが定義した熱力学温度体系。
(トムソンは後にケルビン卿となった、ケルビンとはなじみの深い川の名前)
5.大気圧基準と絶対圧基準
上の式のP1 は絶対圧力で表します。
日常用いる圧力は大気圧基準を多用しますので絶対圧力には換算が必要です。
絶対圧力は単位kPa(abs)で表され、大気圧は101.33kPa(abs)です。
つまり
絶対圧力 = 大気圧基準(Gage圧) + 101.33 kPa(abs) となります。
例: 圧力 0.5 MPa(G) を絶対圧力で表すと
0.5 MPa(G) + 0.10133 MPa(abs) = 0.6013 MPa(abs) =
601.3 kPa(abs)